自社における「多様な働き方」の工夫を模索し、生産性の向上、企業風土の改革に取り組み、仕事と家庭の両立支援を行いましょう!
今回の改正は、仕事と子育ての両立支援を一層高めるために、男女とも子育てをしながら働き続けることができる雇用環境の整備を行い、持続可能な社会の構築を目的としております。
3歳までの子を養育する労働者について、原則として、1日の所定労働時間を6時間にするなど所定労働時間の短縮の措置を講じること、請求があった場合には、所定外労働を免除しなければならないことになりました。
| 改正前 | 改正後 | |
|---|---|---|
| 3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度・所定外労働(残業)免除制度などから1つを選択して制度を設けることを事業主の義務とする。
|
①3歳までの子を養育する労働者が希望すれば利用できる短時間勤務制度(1日6時間)を設けることを事業主の義務とする。 |
※ 労使協定を締結することにより、雇用期間が1年未満の者など一定の者については適用が除外されます。
小学校就学前の子が2人以上の場合には、子の看護休暇を年間10日間取得することが可能になります。なお、同一の子について10日取得することも可能です。
| 改正前 | 改正後 | |
|---|---|---|
病気・怪我をした小学校就学前の子の看護のための休暇について労働者1人あたり年5日の取得が可能。
|
休暇の取得可能日数が、小学校就学前の子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日になる。 |
※ 今後は、子どもに「予防接種や健康診断を受けさせること」も看護休暇の対象になります。
勤労者世帯の半数が共働き世帯となっている現代社会において、女性だけでなく男性も子育てができ、親子で過ごす時間を持つことの環境づくりが求められる中、父親も子育てができる働き方の実現を目指し、以下3点の改正が行われました。
父母ともに育児休業を取得する場合、1歳2カ月(現行1歳)までの間に、1年間育児休業を取得可能とする。
| 改正前 | 改正後 | |
|---|---|---|
父母とも、子が1歳に達するまでの1年間育児休業の取得が可能。
|
母(父)だけでなく父(母)も育児休業を取得する場合、休業可能期間が1歳2カ月に達するまで(2か月は父(母)のプラス分)に延長されます。 |
※ 母の場合の産後休業・育児休業期間を合わせて1年間、父の場合の育児休業期間の上限1年間についての変更はありません。
母親の出産後8週間以内に、父親が育児休業を取得した場合には、特別の事情がなくても、再び育児休業を取得することが可能となりました。
| 改正前 | 改正後 | |
|---|---|---|
育児休業を取得した場合、配偶者の死亡など特別の事情がない限り、再度の取得は不可能。
|
配偶者の出産後8週間以内の期間内に、父親が育児休業を取得した場合には、特別な事業がなくても、再度の取得が可能となる。 |
※ 母親が出産して育児休業を取得する場合には、産後8週間の産後休業期間終了後に育児休業を取得する運用が行われているため、その間、父親が育児休業を取得することが認められております。
労使協定を定めることにより、配偶者が専業主婦(夫)や育児休業期間中である場合などの場合は労働者からの育児休業申出を拒める制度を廃止し、専業主婦(夫)家庭の夫(妻)であっても育児休業の取得が可能となります。
| 改正前 | 改正後 | |
|---|---|---|
労使協定の定めにより、配偶者が専業主婦(夫)や育児休業期間中である場合などは育児休業の申出を拒める制度。
|
労使協定による配偶者が専業主婦(夫)や育児休業期間中である場合などの労働者からの育児休業申出を拒める除外規定を廃止し、専業主婦(夫)家庭の夫(妻)であっても育児休業を取得できるようになる。 |
※ これに伴い、時間外労働の制限規定においても、配偶者が専業主婦(夫)である場合には、時間外労働の制限規定において適用除外とされていましたが、こちらも廃止となります。
労働者が申し出ることにより、要介護状態の対象家族が1人以上であれば年5日、2人以上であれば年10日、介護休暇を取得できるようになります。
● 苦情処理・紛争解決の援助及び調停の仕組みの創設
● 勧告に従わない場合の公表制度及び報告を求めた場合に報告させず、又は虚偽の報告をした者に対する過料の創設
※(1)(4)について常時100人以下の労働者を雇用する企業は平成24年6月30日から施行予定となっております。
改正される育児・介護休業法の育児休業に関する両立支援策のポイントを子どもの出生から小学校就学に至るまでの時系列に置き換えて把握しましょう。
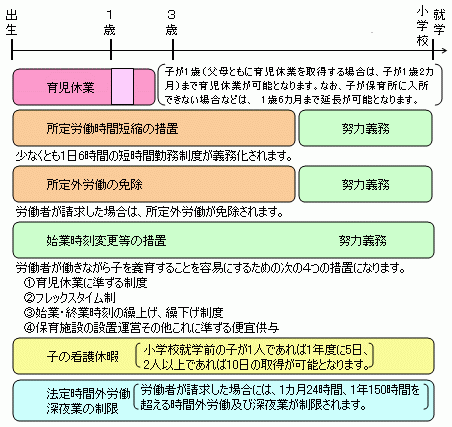
※ 労使協定を締結することにより、雇用期間が短い者など一定の者は適用が除外されます。
今回の改正内容では、新たに義務化される事項、拡充される制度や創設される休暇などの改正事項が数多くございます。改正に伴う就業規則の変更事項も多くなるので、自社制度に落とし込む際には、図式化し横断的に理解するなど実際のフローを把握しなければなりません。改正事項の対応はもちろんですが、健康保険の給付金や厚生年金の養育特例制度などを含め、時系列的な実際の流れをつかんで頂くことが重要です。
雇用期間が短い者や退職が予定されている者、1週間の所定労働時間が短い者など一定の労働者については、労使協定に定め、締結することにより、育児・介護休業に関する適用を除外することができます。各企業の実情や労使間で納得した制度を運用のためにも労使協定の締結が必要です。
育児・介護休業については、子育てや介護支援のための助成金制度がございます。
各企業における実情に応じた助成金制度の活用をご検討ください。
| 助成金の名称 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
中小企業子育て支援助成金
|
常用労働者100人以下の事業主が、育児休業制度を導入し、初めて従業員が利用する | 育児休業1人目100万円 2~5人目まで80万円 |
両立支援レベルアップ助成金 (代替要員確保コース) |
育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業取得者を原職等に復帰させたとき | 原則1人目50万円、 2人目以降15万円 /中小企業の場合 (期間・人数とも制限あり) |
両立支援レベルアップ助成金 (休業中能力アップコース) |
育児休業又は介護休業を取得した労働者が、 スムーズに職場に復帰できるようなプログラムを実施したとき |
1人21万円まで延べ100人まで /中小企業の場合 |
両立支援レベルアップ助成金 (子育て期の短時間勤務支援コース) |
子を養育する労働者のための短時間勤務等制度を設け、利用者が生じたとき | 1人目100万円、 2人目以降80万円 /小規模事業主の場合 (期間・人数とも制限あり) |
両立支援レベルアップ助成金 (育児・介護費用等補助コース) |
労働者が育児・介護サービスを利用する際に要した費用の補助を行ったとき | 育児サービスの場合の 助成率は4分の3 /中小企業の場合 (上限及び期間制限あり) |
※文書作成時点での内容になります。
助成金制度につきましては、頻繁に改正が行われていますので、詳細はご確認ください。